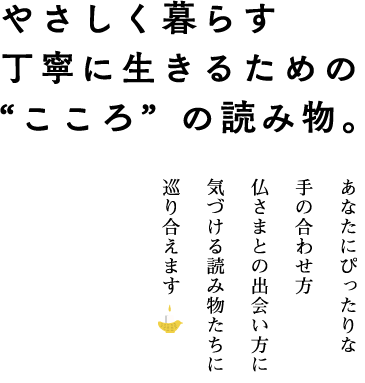Article読み物
【2025年度版に更新】厄年のあなたに贈る!どこよりも分かりやすい厄除け厄祓い完全ガイド

今年厄年を迎えるあなた。
いったいどんな
悪いことが起こるのかと
不安になっていませんか?
また、厄払いに行こうと
考えてはいるものの、
「いつまで行かなあかんの?」
「どこの神社に行ったらええん?」
と、モジモジしている人も
少なくないのでは?
そんなあなたの
不安やモジモジを
素心が解消します。
『こころね』は
厄年について
厄除け厄払いについて
分かりやすく解説いたします。
厄とは何なのか。
厄払いはいつまでに行くべきか。
厄年には何をすべきか。
播磨地方にお住いの方だけでなく
日本全国で
厄年にさしかかっている方にも
役に立つ記事に仕立てました。
どうぞ最後まで読み進めていただき
よき厄年をお過ごしください。
あなただけじゃない! 日本人の8人に1人は厄年
まずは厄年のおさらい。厄年とは一般的に下の年齢のことです(数え年なので、誕生日を迎える前の人は満年齢+2歳、迎えたあとの人は+1歳で計算します)。
【男性】
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
【女性】
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
出典:wikipedexia「厄年」

2025(令和7)年の厄年はこちら。兵庫県神社庁発行の「人生儀礼年表」。白國神社(姫路市)にて。
厄年はどうして厄なのか? 厄年の歴史をさかのぼる
さて、こうした年齢がどうして厄年という風に捉えられるようになったのでしょうか?
昔の厄年は十二支と関係があった?
厄年について記載された古い文献に、天録元年(970年)に成立した陰陽道の書物『口遊』というものがあります。
この中で厄年は、13、25、37、39、61、73、85、91歳が挙げられているそうです。いまでいうところの女性の33歳や男性の42歳が含まれていないのが気になりますが、よく見てみると、一部を除くものの、12年ごとに厄年が巡っていることが分かります。厄年と十二支には大きな関係がありそうです。
民俗学者の新谷尚樹さんによると、昔の人は12年をワンセットとして捉えていたそうです。
12年、24年、36年と、十二支が周回するたび新たなステージがやってくる。そんな時私たちは「気持ちを新たにしたいな」「運気をリセットしたいな」という気になるものです。
そのための境界として厄年が定められたのではないかとも考えられます。
厄年と十二支の関連性は『源氏物語』にも見られます。藤壺や紫の上の厄年(37歳)に触れていることから、女性の37歳が「物忌み」の時期だったと考えられるそうです。
また、室町時代の百科事典『拾芥抄』では、13、25、37、49、61、85、99歳と、やはり12の倍数で厄年が数えられているとのこと。
ちなみに、はじめの厄年が13歳から設定されているのは数え年のため。数え年では生まれた年を1歳、そして誕生日ではなくお正月を迎えるたびに年をひとつ取ると考えます。
現在の厄年の原型は江戸時代から
さて、現在の厄年は十二支との関連があまり見られません。この原型ができあがったのは江戸時代からで、庶民たちが語呂合わせで作ったものだと言われています。
姫路にもなじみの深い東洋大学の創始者でもある仏教学者の井上円了は『迷信と宗教』の中でこう記しています。
十九は「重苦」に通じ、四十九は「始終苦」に通じ、四十二は十を略せば「四二」となる。「四二」は「死に」に通じ、三十三は「惨々」に通ずるから縁起が悪いといわれておる。
江戸時代は、庶民の間でも暦が流行し、陰陽道における年回りなど考慮されずに厄年が浸透していったのです。

姫路の厄除の名所のひとつが男山八幡宮。姫路市をパノラマで一望できます。
厄除けが1月や2月に行われる理由
神社やお寺で行われる厄除けや厄払い。その多くが1月や2月に行われます。ここには、新年の早い段階で厄除けをして一年を無事に乗り切ろうという人々の祈りや願いが見られます。
しかし、1月に行うところもあれば2月に行うところもある。しかも兵庫県内の多くの神社では厄除け大祭はそれぞれ18日と19日の2日間にわたって行われる。これはいったいどういうことなのでしょうか。
厄除大祭が1月や2月の18、19日に行われる理由を、播磨国総社・射楯兵主神社の総務部部長、大惠貴之さんに教えてもらいました。

播磨国総社・射楯兵主神社の大惠さん。厄年についてとても分かりやすく解説してくださいました。
大惠さんによると、毎月19日は厄神さんの縁日なのだそうです。この厄神さんという神様はみなさんが聞いたことのある八幡様のことで、『日本書紀』にも出てくる誉田別命(ほんだわけのみこと)を神格化した神様です。
そしてこの八幡様が、18日から19日に変わる瞬間になんと! 厄神さんに変身して下さるとのこと!
そこから毎月19日が厄神さんの縁日となっていったのだそうです。男山八幡宮の厄神祭が夜通し行われるのはもはや姫路の名物でしたが、八幡宮で、2月18日と19日に、しかも夜通し行われるのは、このためだったんですね(ちなみにコロナ禍以降は夜通しの大祭はとりやめ。残念)。
そしてもうひとつの疑問。どうして12カ月の内の1月と2月なのか。
これは数え年ではお正月がやってきた段階で年をひとつ取るとされてきていたからです。
つまり厄年は、誕生日からではなく、お正月を迎えたその日から始まるということ。新暦の1月や、あるいは旧暦のお正月に該当する2月の縁日に厄除大祭が行われるのはこのためです。
では、「厄除大祭までに厄払いしなくてはならないの⁉」と思われる方もご安心ください。
大惠さんは「厄年とは1年を通してのことなので、その年の早いうちに来てもらいのが理想ですが、気づいたとき、思い立った時でも構いませんよ」と話してくださいます。
実際に11月の七五三のお参りの時に「今年の厄払い、忘れてたわ!」と、一緒に厄払いのお祓いをする人もあったそうです。神様は寛大です。

厄年は「役年」 幸せに生きるための知恵の結晶
「厄年には災厄が降りかかる!」このように考えてしまう人が多いのですが、一方でよく言われているのが「厄」とは「役」であるということ。
会社での役割、家庭での役目。私たちはいろいろな役を背負っています。
女性の30代は出産や子育て、男性の40代というのは仕事において大きな変化や責任が伴う時期です。
また、男女とも還暦は厄年に該当しますが、60歳という年齢も人生の中での大きな大きな節目です。
「厄年の人を秋祭りの屋台の担ぎ手にする地域もあるんですよ」と大惠さん。その地域では厄年の人が「年男」を担うのだそうです。「厄年の人が神様の役をして、厄を払う、そうした風習はいたるところで見られますよ」とのことばに続けて、厄年の本質を次のように話してくれました。
「厄年は、暦の運行と経験則から、「これくらいの年代の時に悪いことが起きそうだな」ということを割り出して作られた、いわば先人たちの知恵の結晶なのです」
変化や節目に向き合うと、私たちはどうしても心身の調子を崩しがちです。そう考えると、大惠さんが話すように、きっと厄年だから悪いことが起こるのではなく、心身が不調になりがちな時期をこそ厄年にしたのかもしれませんね。
あらゆる事柄の変化に差しかかる時期を「厄年」ということにしておくことで、「日々を気を付けて生活しなくちゃ」「まわりの人たちに感謝をして慎ましやかにしておかなくちゃ」と、自らを戒めることだってできますし、何かイヤなことがあった時も厄年のせいにしておくことだってできる。
厄年とは先人たちが編みだした、幸せに生きるためのひとつの知恵なのかもしれません。

厄年勝手にQ&A
この記事を書くにあたり、たくさんの神社やお寺に取材をさせていただきました。そこで語られたことをもとに、厄年に関するQ&Aをまとめました。
Q:厄払いはいつ行けばいいの?
基本的にはいつでも構いません。もちろん厄年はお正月から始まりますので、年の初めの1月2月に行けるに越したことはありませんが、仮に遅くなったとしても、思い立った時にお祓いやご祈祷をしてもらいましょう。
Q:人混みが苦手。大祭を避けてもいいの?
もちろん大丈夫です!大祭はどこも込み合います。大惠さんによると、コロナ禍よりもさらに以前から分散参拝をする人が増えているとのことです。
Q:予約は必要?
予約なしで受け付けてくれるところ、予約が必要なところ、時間が決められているところなど、神社やお寺側の対応もさまざまです。まずは事前に電話やインターネットなどで確認しておきましょう。
Q:前厄・本厄・後厄 3年間とも厄払いしてもらうべき?
「気になる」のであれば、厄払いしてもらいましょう。心の中で気になるかどうか。ここがとっても大切です。
Q:どの神社、どのお寺に行けばいいの?
あなたがお好みの神社やお寺にお願いしましょう。もしも氏神様や菩提寺が受け付けてくれるのであればそれでも構いません。ただし、普段は宮司や僧侶がいないところや、そもそも厄払いをしてないところもあります。事前の確認が大切です。
Q:厄払いの費用は?
神社やお寺によって異なりますが、5千円から1万円が相場です。くわしくは直接問い合わせましょう。
Q:厄払いしてもらう時の服装は?
普段の服装で構いません。
Q:神社からいただいたお守りやお札はどうしたらいい?
お守りは肌身離さず持っておきましょう。お札は神棚がある人は神棚に、ない人は目線より高い位置に立てかけておきます。次の年の初詣に神社に返します。
Q:厄年の人への贈り物はどんなものがいいの?
厄年を迎えた人の健康や無事を祈って贈り物をする風習があります。
長生きへの願いを込めた「長いもの」の場合、男性にはネクタイやベルト、女性にはネックレス、マフラーは男女ともに喜ばれそうです。
龍や蛇のように、脱皮して再生する生き物になぞらえた「うろこ模様」として、財布を贈る人もいます。
そのほかにも開運厄除を願ってのパワーストーンやブレスレット、健康グッズなども好まれます。
ちなみに射楯兵主神社では、特別祈祷した人への「長いもの」の縁起物として、ファイテン社と共同開発したネックレス、または明珍火箸を授けるそうです。


ファイテン社と共同開発のネックレス(上)と明珍火箸(下)。発想が面白い!
いかがでしたか?
厄年は、私たちが幸せに生きていくための日本人の智慧。お祓いや祈祷をしてもらい、あなたの身の丈にあった生活を心がけるようにいたしましょう!
みなさまの穏やかな日々をお祈りいたします。

【取材先・参考図書・文献・サイト】
今回全面的に取材のご協力を下さった播磨国総社・射楯兵主神社さま。本当にありがとうございます。総社の厄除大祭は2月18日と19日です。
また、この記事を執筆するにあたり参考にさせていただいた書籍や文献をご紹介いたします。この場をお借りして感謝申し上げます。
●井上円了「迷信と宗教」青空文庫
●島田裕巳「「厄年」はある!」三五館(2005)
●新谷尚樹「日本人の縁起かつぎと厄払い」青春出版社(2007)
●厄除八幡宮(宗佐厄神)ホームページ
構成・文・撮影:玉川将人